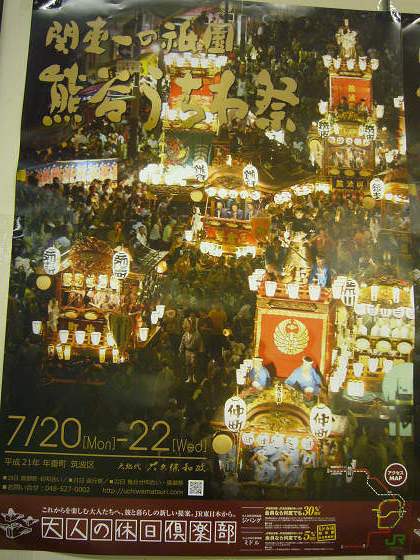|
初日の午前中、御神輿の渡御を迎える為、各町のお囃子が街中に響き渡る。 (午前9時35分頃撮影) |
 |
仲町区の山車がお囃子を演奏して迎える中、八木橋デパート裏、熊谷寺前を御神輿が通過していく。 (午前10時05分頃撮影) |
 |
一旦休憩した後、ここからお祭り広場まで最後のひと踏ん張り。 (午前10時20分頃撮影) |
 |
御神輿を迎える、第二本町区の山車。 囃し方のお姉さん達の楽しそうな表情がいい。 そういえば、昼間だから屋根ににわとりが乗っていますね。 (午前10時30分頃撮影) |
 |
御神輿は国道17号線を横断して、間もなくお祭り広場へ。 (午前10時40分頃撮影) |
 |
お祭り広場へ到着した御神輿。 ここで、2〜3周してから御仮屋へ入った。 (午前10時40分頃撮影) |
 |
渡御着輿祭にて、祝詞を読み上げる熊谷八坂神社宮司。 (午前11時00分頃撮影) |
 |
(午前11時00分頃撮影) |
 |
晴れ渡った夏空と御仮屋。 この天気が三日間持てば良かったのですが。 (午前11時10分頃撮影) |